お腹の膨満が、頭痛やパニック障害を引きおこす
胃腸が膨満すると、腹痛や便秘や胃酸の逆流などといった症状だけでなく、パニック障害や頭痛、アレルギーや喘息などといった様々な症状を引きおこす恐れがあります。
弛緩性便秘
腸内の便を押し出すには、腸管を収縮させる必要があります。
ところがガスで膨満していたら、腸管を縮めることができません。そのため便秘になります。この便秘は「弛緩性便秘」といいます。
治すにはガスを減らす必要があり、それには『ガスの発生源となる食品』をできるだけ摂らないことが大事です。
ガスを発生する食品成分は、次の5つです。
- 乳糖
- 果糖
- レジスタント・スターチ(難消化性デンプン)
- 食物繊維
- 人工甘味料
概して便秘で困っている人たちは、努めて食物繊維を多く摂ろうとしていますが、それが逆効果になるのです。野菜や豆類、芋類、キノコ類、雑穀類などをたくさん食べるほど、胃腸内で食物繊維が発酵してガスがたくさん発生するのです。その結果、膨満するのです。
とくに大腸の横行結腸はガスが溜まりやすい部位で、そのすぐ後ろに胃があります。横行結腸がガスで膨満すると、胃が押されて胃酸が逆流します。
そして胃酸が逆流すると、食道がただれて炎症がおきます。すると、咳が出たり胸焼けがおきたりするようになります。
パニック障害
呼吸は、横隔膜が下がることによって息が吸えて、横隔膜が上がるときに息が吐き出されます。ところが過剰な腸内ガスによってお腹が膨満すると、腹圧によって横隔膜が押し上げられて、息を吸いにくくなります。
こうして息が十分に吸えなくなると、脳は交感神経を緊張させます。すると副腎からアドレナリンが分泌されて、気管支が拡張します。気管支の拡張によって、いくらか酸素を取り込みやすくなりますが、一方で、アドレナリンによって血管が強く収縮し、心臓のポンプ力が強くなり、心身が興奮状態になります。その結果、心臓がバクバクして(頻脈)血圧が高くなり、夜眠れなくなります。
すると、呼吸が自ずと浅く速くなります。速い呼吸を続けていると「過呼吸」になり、血液中の二酸化炭素が減少します。すると全身がチクチクしたりしびれたりして、震えや痙攣、動悸、発汗、めまいや胸痛といった症状が現れて、激しい不安や恐怖に襲われます。これが「パニック発作」といわれる症状で、パニック発作を頻繁にくり返すのが「パニック障害」です。
パニック障害には通常、精神安定剤やβブロッカーが処方されますが、薬はあくまで症状を抑えるだけで原因を改善するわけではありません。
動悸も頻脈も高血圧も不眠も不安や恐怖も、すべてアドレナリンによる症状です。
なぜ、アドレナリンが多量に放出されるのでしょうか?
膨満によって横隔膜が押し上げられたままになると、息が十分に吸えないから、気管支を拡張させるためにアドレナリンが分泌されるのです。
つまり、膨満から発症するのです。
ガスが発生するのは、発酵したからです。発酵するとガスのほか、乳酸も生成されます。胃腸内の発酵によって生じた乳酸が血液に吸収されると「乳酸アシドーシス(酸性化)」になり、パニック発作を誘発します。つまり乳酸も、パニック発作を引きおこす原因の一つなのです。
要するに、消化されない糖質(乳糖・果糖・レジスタントスターチ・食物繊維・人工甘味料)を腸内細菌が食べると、発酵してガスと乳酸が生成されるのです。その結果、お腹が膨満して、横隔膜が押し上げられて息が吸いにくくなるためアドレナリンが分泌されて、さらに血液中に乳酸が増えることで、パニック発作が誘発されるのです。
したがって、野菜や豆類、芋類やキノコ類、雑穀などをたくさん食べるほど、パニック発作をおこしやすくなるのです。
アレルギーと膠原病
花粉症やアトピー性皮膚炎や喘息といったアレルギー症状も、関節リウマチや橋本病、潰瘍性大腸炎やクローン病、多発性硬化症や重症筋無力症、原発性胆汁性胆管炎やシェーグレン症候群などといった膠原病(自己免疫疾患)も、ひとことで言えば「炎症」です。
炎症は、免疫力が強くなるほど悪化します。免疫細胞がアレルゲンや体内の特定の部位を攻撃すると炎症がおきるので、免疫力が強くなるほど炎症が激しくなるのです。
そして免疫力は、副交感神経が優位になると増強します。反対に、交感神経が緊張すると免疫力が低下します。
つまり、『副交感神経⇒免疫力増強⇒炎症増大⇒症状悪化』となるのです。
副交感神経は低気圧でも緊張しますが、お腹が膨満するだけでも緊張するのです。
1955年、エジンバラ大学のエインズリー・イゴ博士は、腸に小型のバルーンを挿入し、バルーンを膨らせると副交感神経(求心性迷走神経)が緊張することを見出しました。(Iggo A, Journal of Physiology 128,593-607,1955)つまり、栄養成分や酸アルカリといった刺激がなくても、ただ腸が膨らむだけで副交感神経が緊張するのです。
要するに、胃腸が膨満することによって副交感神経が緊張して、免疫力が強く働くため、炎症が増大するのです。したがって、野菜や豆類、芋類やキノコ類、雑穀などをたくさん食べるほど、アレルギーや膠原病の症状が悪化するのです。
慢性頭痛
代表的な慢性頭痛に、「偏頭痛」と「緊張型頭痛」があります。
偏頭痛は、脳の血管が拡張しておきます。ですから入浴や運動、ポリフェノールなどによって血管が拡張すると、偏頭痛が誘発されます。
また、お腹の膨満によって副交感神経が緊張すると血管が拡張するので、偏頭痛がおきやすくなります。
緊張型頭痛は、頭が締め付けられるような痛みが特徴です。主な原因は、酸欠や低血糖と考えられます。
偏頭痛と緊張型頭痛のほか、非常に激しい頭痛や眼痛を引きおこすのが「血管の攣縮」による頭痛です。血管が痙攣によって強く収縮することによって、血流が著しく減少して激しい痛みがおきます。
なぜ、血管が攣縮するのでしょうか?
私は、アセチルコリンの過剰によって引きおこされるのではないか、と考えています。
アセチルコリンは様々な作用をしている神経伝達物質で、記憶や学習を助ける作用、自律神経を介して内臓をコントロールする作用、筋肉に運動司令を伝える作用、脳内炎症を抑える作用などが知られています。
これだけ重要な作用を担っているので、とても良い物質であるかのように見えます。しかし、アセチルコリンの受容体をみると、決して良いことだけをする物質とはいえないことが分かるでしょう。
アセチルコリンの受容体は2種類あって、一つは「ニコチン受容体」、もう一つは「ムスカリン受容体」です。ニコチン受容体は筋肉に、ムスカリン受容体は内臓に存在し、脳と自律神経には両方の受容体があります。
ニコチンはタバコに含まれる成分で、血管を強く収縮させる作用があります。
ムスカリンは毒キノコの毒成分で、神経を麻痺させて痙攣を引きおこす作用があります。
アセチルコリンがニコチン受容体やムスカリン受容体に結合するということは、アセチルコリンとニコチンとムスカリンは似ているということです。
ニコチンや毒キノコの毒に似ているアセチルコリンが、もし過剰に放出されたら、どういうことがおきるでしょうか?
例えば、キリキリと差し込むような激しい腹痛は「疝痛」といって、過剰なアセチルコリンによって腸が痙攣しているのです。疝痛ほど激しい痛みがなくても、下痢や吐き気や嘔吐、食欲不振などといった症状は、アセチルコリンの過剰によって引きおこされます。
同じことが、脳の血管にも起こりえます。過剰なアセチルコリンによって脳の血管が攣縮すると、激しい頭痛やめまいがおきるでしょう。
では、なぜアセチルコリンが過剰に放出されるのでしょうか?
アセチルコリンが過剰になる原因には、コリンエステラーゼ阻害剤、アルツハイマー治療薬、重症筋無力症治療薬、パーキンソン病治療薬、有機リン系農薬中毒などが知られていますが、それ以外に「腸の膨満」も考えられます。
腸が膨満することで副交感神経が緊張すると、神経伝達物質のアセチルコリンが大量に放出されます。それによってS状結腸が痙攣して異常に細くなることで便秘になったり、疝痛を引きおこしたりして、さらに迷走神経を介してアセチルコリンが脳に伝わると頭や眼に激しい痛みを引きおこすのではないかと推測されます。
ということは、野菜や豆類、芋類やキノコ類、雑穀などをたくさん食べるほど食物繊維が胃腸内で発酵してガスが大量に発生して膨満し、副交感神経が緊張することでアセチルコリンが大量に放出されて、疝痛や頭痛がおきやすくなるわけです。
喘息とCOPD
アセチルコリンは、呼吸にも深く関わっています。気管支を収縮する作用があるため、喘息やCOPD(慢性閉塞性肺疾患)などの呼吸症状を悪化させる原因となります。
例えば、風邪やインフルエンザの感染や喫煙などによって気道上皮が傷害されると、アセチルコリンが過剰に放出されて、気管支が収縮して呼吸困難が引きおこされます。
そういうときに野菜や豆類や芋類やキノコ類、雑穀などをたくさん食べると、食物繊維が胃腸内で発酵してガスが大量に発生して、お腹が膨満します。すると膨満によって横隔膜が押し上げられて息が吸いにくくなるだけでなく、副交感神経の緊張によってアセチルコリンが放出されて気管支が収縮するので、さらに息が吸えなくなってしまいます。
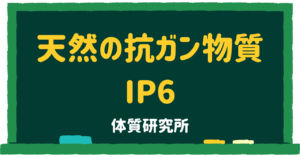
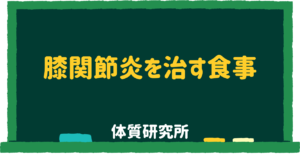
小学生から過呼吸がたまに出るようになり43歳の今もずっと息苦しさが続いていますがリーキーガットが原因だったとは目から鱗でした。
7月からディフェンシブフード実践しています。
ウルソも重曹も飲み始めました。
パニック回避のため4年前からメガビタミン実践していましたがホエイプロテインと乳製品なので飲まない方がいいですか?
いずれはビタミンもプロテインも飲まずの生活を目指していますがまだまだ不安感と息苦しさがあります。
プロテインはの間違いです。すいません。
ホエイプロティンは飲んでも大丈夫ですが、パニック発作を防ぐためにプロテインは必要ありません。
一番大事なのは腸内ガスを減らすことで、それにはできるだけ食物繊維と乳酸菌を摂らないことです。詳しくは「乳酸菌が病気をつくる」(知道出版)に解説していますので、ぜひお読みください。
また、体質研究所で販売している腸内細菌を減らすサプリ(ガットサポート、フローラサポート)をお勧めします。
お忙しいなかお返事ありがとうございます。
自律神経を整える食事、リーキーガット解消法読みました。乳酸菌が病気をつくるを注文中です!
プロテイン飲むのをやめます。
パニックとアレルギーを完治したいです。
グルタミンも飲み始めました。
松原式経口補水液も毎日飲んでます。
サプリもチェックしてみます。
ありがとうございました。
この動画も参考にご覧ください。
https://youtu.be/IXqBhA0vXCo?si=S8cUO3IcjHFW7GI9
みてみます!
ありがとうございます