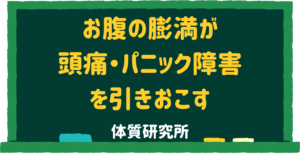膝関節炎を治す食事
ある日突然、膝が激痛に襲われて歩けなくなっても、整形外科や接骨院や鍼灸院などで食事や栄養の指導を受けることはないでしょう。
しかし本当に治したければ、食事を見直すとともに、関節の破壊を防ぐ栄養を十分に摂る必要があるのです。食事はどのように直せばよいのか? また、関節の破壊を防ぐ栄養とは?を解説します。
関節が変形する原因
関節に激痛がおきて、徐々に変形していくのが「変形性関節症」です。なぜ、関節が変形していくのでしょうか?
動きすぎて、関節がすり減ってしまったからではありません。また痛いのは、骨と骨が当たるからではありません。骨には痛みを感じる神経がないので、骨と骨が当たっても痛くはありません。
関節に激痛がおきて変形していく原因は、血流が悪いことです。
関節への血流が悪いと、軟骨の弾力性が低下していきます。
弾力性が失われてカチカチ・カヒカヒになった軟骨は、徐々に剥離していきます。
剥離した軟骨のカケラが関節内に浮遊し、やがて関節を包んでいる滑膜に刺さります。
すると滑膜に炎症がおきて、激痛が生じます。
そして、炎症がおきた滑膜から「炎症性サイトカイン」が放出されます。その炎症性サイトカインによって、軟骨細胞が死滅していきます。それによって軟骨がどんどん減っていき、関節が変形していくのです。
整理すると、次のようになります。
[血流不良→軟骨の弾力性低下→軟骨の剥離→滑膜炎→炎症性サイトカイン放出→軟骨細胞の死滅→関節の変形]
血流が悪くなる原因
なぜ、血流が悪くなるのでしょうか?
脚の血流が悪くなる原因の大半は、「腸」にあります。脚にくる血液はすべて、腹部を通過してきます。
もし腸が過剰なガスによって膨満したら、脚に向かう血管は押しつぶされてしまいます。そのため、脚への血流量は少なくなります。
とりわけ膨満しやすい箇所は、盲腸とS状結腸です。盲腸は右の下腹部にあり、S状結腸は左の下腹部にあります。
食事をして約2時間後に、小腸で消化吸収されなかった残りが盲腸に流入します。盲腸には大量の腸内細菌が待ち受けていて、流入した内容物を腸内細菌が分解していきます。腸内細菌による分解は、消化ではなく「発酵」といいます。発酵するとガスが発生します。
盲腸で猛烈に発酵すると、ガスが大量に発生して膨満します。すると右脚への血管が圧迫されて、右脚への血流量が少なくなります。
また盲腸で発生したガスは、上行結腸→横行結腸→下行結腸と移動して、最後はS状結腸に溜まってS状結腸が膨満します。すると左脚への血管が圧迫されて、左脚への血流量が少なくなります。
つまり、右脚も左脚も血流が悪くなる原因は、大腸の過剰発酵による「膨満」にあるのです。発酵によって生じた大量のガスで膨満した腸が、脚に向かう血管を圧迫して、脚への血流量を減少させているのです。その結果、膝が悪くなるのです。
過剰発酵の原因
大腸でガスを大量に発生させるのは、小腸で消化吸収されなかったものです。つまり、消化酵素で分解されないものが、大腸で腸内細菌のエサになるのです。
消化酵素で分解できない成分は、次の5つです。
- 乳糖
- 果糖
- レジスタント・スターチ(難消化性デンプン)
- 食物繊維(セルロース、イヌリン、フラクタン、オリゴ糖など)
- 人工甘味料(アスパルテーム・アセスルファムK・キシリトールなど)
これらの成分をたくさん摂るほど、腸内で大量のガスが発生して、お腹が膨満するのです。そして脚への血流が減少することで、膝が悪くなっていくのです。
この5つの成分のなかで、努めて多く摂ろうとしているのが食物繊維でしょう。食物繊維は腸内をきれいにすると言われていますが、実は、食物繊維をたくさん食べると腸内のガスが増えてお腹が膨満することで、脚への血流が悪くなり、膝の痛みと変形が悪化していくのです。
ですから膝を治すには、野菜や豆類や芋類、キノコ類やタケノコや雑穀などといった食物繊維が多い食品をできるだけ食べないようにすることが大事なのです。
骨が破壊されていく原因
膝の炎症が悪化すると、軟骨だけでなく、骨まで破壊されていきます。なぜ、骨が破壊されていくのでしょうか?
骨を破壊していくのは、骨タンパクを分解する酵素です。
その酵素は、細胞内の「リゾゾーム」から放出されます。細胞内には、遺伝子を収納した核や、細胞のエネルギー(ATP)を生成するミトコンドリアをはじめ、様々な小器官があります。リゾゾームもその一つです。
「リゾ」は「溶かす」の意、「ゾーム」は「物」の意のギリシャ語です。つまり「溶かすもの」で、細胞内の異物をすべて溶かし去るための顆粒です。リゾゾームの内部には、カテプシンや酸性フォスファターゼ、酸性デオキシリボヌクレアーゼ、酸性リボヌクレアーゼなどといった分解酵素が40種以上も含まれていて、それらの酵素は酸性の環境で働きます。
過酸化脂質や紫外線や衝撃などによってリゾゾームの膜が破れると、リゾゾーム内の酵素が細胞内に出てきます。しかし正常な細胞内のpHは弱アルカリ性なので、細胞質が分解されることはありません。
ところが、お腹の膨満によって脚の血流が悪いと、膝の細胞内は酸欠になってブドウ糖が解糖されるので「乳酸」が生じます。乳酸によって細胞内が酸性になると、リゾゾーム酵素が働いて、細胞質が破壊されていきます。
つまり、血流不良による酸欠で細胞内に乳酸が増えて酸性になったところで、骨細胞のリゾゾーム膜が破壊されると、リゾゾーム酵素によって細胞が溶かされて、骨が破壊されていくのです。
リゾゾーム膜を強化するビタミンE
リゾゾームの内部には、すべての異物を溶かしてしまう酵素が詰まっています。ですからリゾゾーム膜を強化して、破れないようにすることが大事です。
例えばステロイドには、リゾゾーム膜を強化する作用があります。しかし、ステロイドをずっと使い続けると副作用がおきますので、望ましくはありません。
ですからステロイドではなく、栄養でリゾゾーム膜を強化することが望ましいでしょう。
リゾゾーム膜を強化する働きがあるのが、ビタミンEです。ビタミンEには強い抗酸化力があり、炎症を防ぎ、血管の弾力性を回復させる効果もあります。
ビタミンEは8種類あります。
まず、トコフェロールとトコトリエノールに大別されます。それぞれにα(アルファ)、β(ベータ)、γ(ガンマ)、δ(デルタ)の4種類ずつありますから、全部で8種類あります。
通常、ビタミンEのサプリメントに使われているのは小麦胚芽油で、αトコフェロールが多く含まれています。αトコフェロールを毎日400IU(IU=国際単位)摂ることで、身体の酸化を防ぎ、血管の弾力性を高め、細胞膜やリゾゾーム膜を強化することができます。
ちなみに、8種類あるビタミンEのなかでもっとも高い抗酸化力があるのはδトコトリエノールで、αトコフェロールの約50倍も高い抗酸化力があります。
ビタミンEは脂溶性なので、食事と一緒に摂ると吸収率が高くなります。しかし、胃腸からの吸収率はさほど高くはありません。ところが、皮膚からは100%吸収されます。
そこで体質研究所では、δトコトリエノールをたっぷりと配合した『ロイヤルアメイジング・クリーム』を使ったマッサージを推奨しています。『ロイヤルアメイジング・クリーム』を膝にすり込めば、患部にダイレクトにビタミンEを補給できます。
体内でビタミンEの抗酸化力が働くには、タンパク質を十分に摂る必要があります。筋肉でも骨でも、主な材料はタンパク質だからです。タンパク質の摂取源は、レクチン(植物毒)や食物繊維が多い植物性より、肉や魚や卵といった動物性タンパク質が望ましく、吸収率も動物性のほうが圧倒的に高いです。
反対に、せっかくのビタミンE効果を減殺させてしまう栄養素もあります。それは「鉄」です。鉄は酸化しやすいので、ビタミンEを酸化させて効力を失わせてしまうのです。ですから、鉄のサプリメントと一緒に摂ることは避けたほうがいいでしょう。